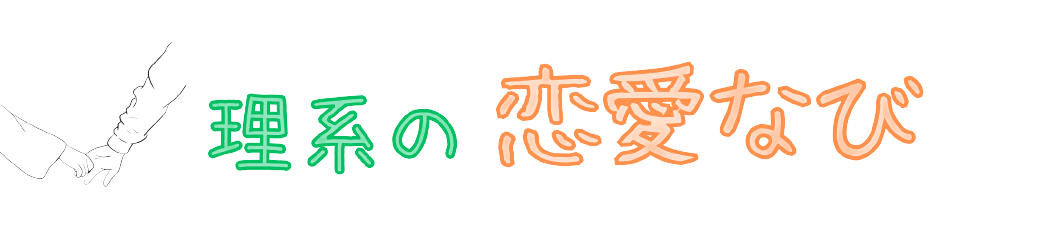どうすれば人と仲良くなれるんだろう…
友達のつくりかたがわからなくなっちゃった
この記事では、そんな悩みを解決できます。
なぜなら、友達0の高校時代から、コミュニケーションを学んで初対面でも関係を築けるようになった私が、心理学を根拠に仲良くなる方法を解説するからです。
そこで今回は、「仲良くなるまで」に活用できる心理学を3つだけ紹介します。
この記事を読み終えると、「どんなことを話せばいいのか」「どんなアクションをとれば仲良くなれるか」がわかり、仲良くなりたいと思った人と自由自在に仲良くなれるようになります。
自然と愛されるコミュ力がほしい人
心理学的に仲良くなる方法3選
人と仲良くなるために知ってほしい心理学的な手法は、大きく3つあります。
人と仲良くなるために役立つ3つの心理学
- 返報性の原理
→好意の返報性
→自己開示の返報性 - 類似性に関する研究
- 認知劇不協和の解消
2つの返報性の原理

返報性の原理とは、何かをもらったとき「お返しをしたい」と感じてしまう心理です。
例えば、誕生日にプレゼントをもらった時。
プレゼントをもらうと、プレゼントしてくれた人の誕生日に、何かお返ししようと思う人は多いんです。
例えば私は、普段プレゼントをあげたりしません。もらうことも少ないです。
プレゼントするにしても食事をご馳走したり、コンビニで奢ったりと、特別プレゼントを選んだりはしません。
しかし最近ありがたいことに、高価なワインなどをプレゼントしてくれる友達が増えてきました。
そしてそういった特別なプレゼントをもらうと、「この人の誕生日にはお返しをしないとな」と思う自分に気づき、「これが返報性の原理か〜」と実感しました。
このように、何かをもらった時にお返しをしたいと思う心理が返報性の原理です。
具体的な物品以外にも、返報性の原理ははたらきます。コミュニケーションでは、次に紹介する2つの返報性の原理が便利です。
2つの返報性の原理
好意の返報性
自己開示の返報性
[好意の返報性]傾聴の重要性
「好意」も、もらったらお返ししたいという心理がはたらきます。
好意にも種類がありますが「好きな気持ち」はわかりやすいですね。
こんな話をご存知でしょうか。
「相手を好きになったのはいつから?」という質問への答えの半数が、「相手に好意を伝えられた後から」だったそうです。
これは「好意をもらったから、相手にも好意をお返ししたい」という好意の返報性がはたらいた結果。
より身近な例を挙げると「親切に〇〇してくれた (好意を受け取った)」という場面。
例えば、「話を聞いてくれた」というシチュエーションでも、好意の返報性ははたらきます。
「(話を聞いて)理解しようとする行動」は「あなたに興味がありますよ。好意を抱いていますよ」というサインになるからです。
この結果「自分に好意を持ってくれる相手のことも、理解してあげたい」という好意の返報性がはたらきます。
好意の返報性が積み重なると、互いの理解が深まっていくので、だんだんと仲良くなっていくんですね。
[自己開示の返報性]相手が話しやすい状況づくり
次に紹介するのは、自己開示の返報性。
自己開示の返報性を理解すると、相手が話しやすい状況を作れるようになります。
例えば、初対面の人に「はじめまして、お仕事は何をしているんですか?お住まいは?恋人はいますか?」などと、いきなり根掘り葉掘り聞かれたら警戒しますよね?
一方で、「はじめまして、今は静岡で暮らしながら、営業で車を売っているたかしといいます 〇〇さんはどんなお仕事を?」と聞かれたらどうでしょう?
おそらく、最初にされた質問攻めよりも、しゃべりやすいのではないでしょうか。
このように、自己開示をすると、相手は自己開示がしやすくなります。
これは「相手が自己開示してくれたから、私も自己開示しないとな」と返報性の原理がはたらくからです。
このように、自己開示を使うと、相手が話しやすくなるので、コミュニケーション上手になれます。
類似性に関する研究
次に紹介するのは、類似性に関する研究*1です。
距離を縮めるには共通点を探そうと言われますよね。
なぜなら、考え方や価値観などで共通点があると、関係性が発展しやすいからです。
例えば私はBUMP OF CHIKENがとにかく好きなので、BUMP好きだといってくれる人と出会うだけで信頼がバク上がりします。
このように、共通点を見つけるだけで「あ、この人は同じ考え方をもった人なんだな」と安心感と信頼感を感じられます。
だから、会話で積極的に共通点を見つけていけば、相手と仲良くなれます。
*1:共通点さがしに関する研究
- 論文
Newcomb, T.M. 1953 An approach of the study of communicative acts. Psychological Review, 60, 393-404.) - [日本語]参考論文
https://secure.ritsumei.ac.jp/ss/sansharonshu/assets/file/2004/40-3_monden.pdf
共通点が見つからなかったらどうするの?
どうあがいでも共通点がみつからない人もいると思います。
その場合は、違いを持つ相手の価値観を楽しむことで、相手を理解してあげましょう。
その結果、返報性の原理で解説したように好意の返報性が働き、相手はあなたに信頼感を感じられます。
相手の違いを楽しむ?どういうこと?と思った方は、ぜひプロカウンセラーの聞く技術を読んでみてください。
人の話を、まるで物語や本を読むように楽しめる聞き方の極意が記されています。
認知的不協和

最後に紹介する心理学用語は認知的不協和。
簡単に言うと「助けてあげた人に好意をもつ」という心理。
助けてくれた人ではなく助けてあげた人に好意をもつのがポイント。
例えば、ダメダメな男性に尽くしてしまう女性は、「お金や物、生活などを助けてあげる」という、「相手を助ける行動」が積み重なった結果であると言われています。
このように、助けた相手を好きになる心理が認知的不協和です。
「認知的不協和」についてはDaiGoさんの本が参考になりました
認知的不協和のコミュニケーションへの応用
コミュニケーションへの活用は簡単です。
なぜなら、相手に助けてもらうシチュエーションを作ればよいだけだから。
覚えておくべきフレーズは「〇〇を教えてください!」
「〇〇を教えてください」は、相手に頼るシチュエーションを一瞬で作れる便利な言葉です。
例えば、「エクセルで〇〇したいんだけど教えてくれない?」「この機械の使い方教えてくれませんか?」などなら、簡単に実践できそうですよね。
このように、「相手に助けてもらう」と認知的不協和がはたらきます。
この結果、相手はあなたに好意を感じてくれるので、信頼関係が築かれていきます。
また私の経験則ですが、こちらから頼れば、相手からも頼られるようになります (返報性の原理ですかね) 。
この「頼る頼られる」というサイクルに入ると、互いに相手への好感を感じられる理想の関係になります。
まとめると、とにかく自分から助けを求めるというアクションを起こしてみましょう。
その小さな勇気が、関係づくりの第一歩になります。

PCスキル、ファッションや映画など、相手の得意分野を普段からチェックしておくことをオススメします。「Aさんはパソコンに詳しいから、パソコンのエラーがでたら聞きに行こう」と、頼るシチュエーションを作りやすくなるからです。
3つの心理学を学んで、仲良くなる方法を実践しよう!
この記事では、人と仲良くなるために活用できる心理学を紹介しました。
- 返報性の原理→自分から好意を伝える言葉や行動が大切
- 認知的不協和→自分から助けを求める姿勢が大切
この二つを意識すれば、確実に相手と仲良くなれます。
とはいえ、現実は心理学のとおりにはいかないのも事実。
そこで当サイトでは、理系コミュ障だった私が、王道のコミュニケーション能力UPの方法を紹介しています。
「人と仲良くなりたい、一期一会をものにしたい」その一心で学んだコミュニケーション方法を「コミュ障の治し方10ステップ」で全てまとめていますので、ぜひチェックしてください。