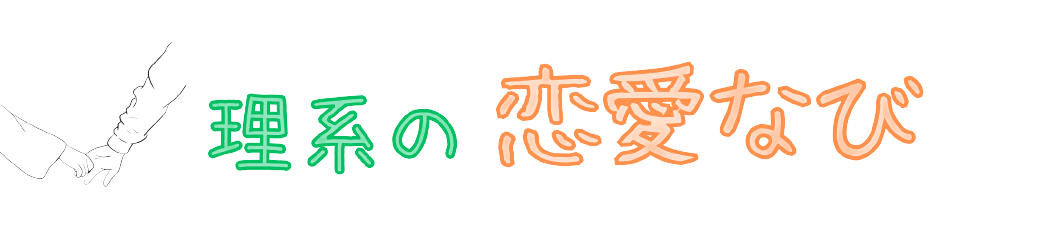会話テクニックを羅列しているだけのテクニックの溜まり場になっています。
真に共感されると嬉しい
合わないであろう、そう諦めていた自分の価値観と、似た人と出会って、はじめて共感を貰えたような、それほど嬉しい気持ちになった。
思えば、中学から大学まで、共感を得たことは無かった。価値観がやや特殊だからだ。
人に怒ることはなく、全て自分の課題と捉えられる。
強みと思われがちだが、「怒りたいことないの?」と言われても何も無く、「本音を出さないよね」と言われる。そうでは無いのに。
それをわかってくれる人が上司であった。会話の端々から「あ、この人はホントに分かってる人だ」と思える思考の跡を感じる。
これこそが共感だと、ホントの共感を知った。形だけでは無い、真の共感。
百聞は一見にしかず、テクニックで共感しようとするのではなく、この嬉しい気持ちを与えられるような真の共感をできるようになりたいと思った日であった。
完全一致の価値観は珍しい。だからせめて、価値観を理解し、共感できる人でありたい。
他の人と違うと思われる話の広げ方
相手に質問したりするなどで話を広げる時、その方向性によって大きく3つの種類がある。
相手が話したいと思える話題、距離が縮まる話題
当たり障りのない話題(天気)
イラッとする話題(トラウマ)
イラッとする話題は論外だが、当たり障りのない話題も長期的に見れば全くもって意味が無い。
メラビアンの法則の誤解
メラビアンが行った実験の内容
メラビアンは2つの実験を行いました。
1つ目の実験では、「そうかもしれない」という意味の”maybe”を口調の強弱や表情を変えて言われた時、印象に変化があるのかを検証しました。
実験では、強い口調で言われた方が普通の口調で言われるよりも説得力が増すという結果が得られました。
2つ目の実験では、まず被験者に「好き」、「嫌い」、「普通」からイメージする単語を3つずつ選ばせました。
次に、それらの合計9つの単語を、それぞれ「好き」、「嫌い」、「普通」を連想させる声色でレコーダーに録音しました。
さらに、「好き」、「嫌い」、「普通」を連想させる顔写真を1枚ずつ用意しました。
そして、被験者に写真を見ながら録音した音声を聞いてもらい、その後どのような印象を感じたか質問しました。
実験の結果、言語情報、聴覚情報、視覚情報が一致しない時には、視覚情報が最も優先され、次いで聴覚情報、言語情報の順番に優先されるとわかりました。これが前述の3Vの法則です。
NTTコムウェア
メラビアンの法則では、あくまで情報に矛盾が生じた時に優先される情報を調べただけです。
言い換えると、一貫性の法則が崩れた時に、どの情報が優先されるかを調べた実験と言えますね。
ここからは分野違いの研究者である私の考察なので悪しからず。
考察1.結局見た目が重要
3つの情報の矛盾をできる限り減らす努力はできるが、完全に矛盾がないなんてことはほぼない。
なら、矛盾が生じる前提で、矛盾が生じた時に重視される見た目を磨いておくのはとても大切。
考察2.見た目・聴覚情報・言語情報の矛盾がなくて初めて、相手にアピールする土台が完成する。
人との関係構築は結局のところ言語による関係の深化。
3つの情報に矛盾が生じた時点で自分のアピールしたい言語の内容部分が耳に入ってこなくなるわけだから、3つ全てに気を使って初めて言語の部分を聞いてもらえる。
共感上手になるための共感方法
「共感した瞬間だけは相手が笑顔になってくれるけど、その後の会話が続かない!」と悩む人に、一歩先の共感テクニックをお伝えします。
それは、話に含まれる複数の感情に対して共感するテクニック。
例えば「先日ライブに行ってきたんだ!」と興奮気味に話す友達にどんな共感の言葉をかけますか?
「楽しかったね」はもちろん、「登場する数分間の心臓が張り裂けそうな緊張感」「ライブが終わったあとのなんとも言えない寂しさや悲しさ」など、一見すると「楽しい」とは正反対の感情も実は存在しています。
実際に私自身、会話のピークが落ちてきたなと思った時には、”多少不自然な会話の流れ”であっても他の共感の言葉を繰りだせば、相手は楽しく話しだしてくれます。
このように、相手の言葉に含まれるたくさんの感情を拾い上げられるようになると、まだまだ相手は話してくれるようになります。
参考図書:会話が途切れない!やっぱり大事 46のルール "P30より" (私のレビューに飛びます。)
コミュニケーションに関する心理学
練習の優先度:★
目的:テクニックの意図を深く理解する。コミュニケーションに潜む不安をなくす。
参考記事:心理学的に人と仲良くなる方法
深い関係を築くための会話術
相手が話してくれた情報を忘れない
自分が最も大切にしているアーティスト、思い出、人間関係を一度話したとしましょう。
それを忘れられたら悲しいですよね。
相手も同じ。人によって忘れてほしくない話題は違いますが、それが些細な話題という人もいます。
相手が些細なことであっても忘れてほしくない人であるなら、忘れない努力が大切でしょう。
whyを聞き出す
「なぜ楽しかったのか」「なぜそれをしたのか」まで聞き出しておくと、関連づけができるため、記憶に残りやすいです。
抽象度を上げて共通点を見出す。
◯◯さんは私と共通点がある、と考えられると、忘れづらく、お互いに親近感UPにつながります。
「特に関わりづらい人とは、小さな共通点をたくさん(質より量)見つけると良い」
たしかに「思考や考えが一致する」上司などとは、かなりコミュニケーションを取りやすい。
会議などでも「私の考えも基本的に似ているのですが、」というと、相手は味方であると感じてくれるので、うまく会議が進みやすい(参考:コミュトレ)
ただあくまで、根底に共通点があると考えておき、「共通点を見つけるゲーム」にしてはいけない。
共通点の見つけ方として、抽象度を上げることによって、大まかには共通点と言えるような会話に持っていく。これなら「共通点がある」と考えることができるようになるので、忘れづらく、お互いに親近感UPにつながる。
相手の話に共感するテクニックに関する考察
大前提として、価値観が同じ人・そうでない人、それぞれに適用できるテクニックです。あえてこれを伝えたのは、価値観が違う、理解できない、とならないようにするためです。
結論から述べると、入試における国語の問題を解くイメージ。登場人物の視点に立つ、という共感方法です。
私は高校入試の問題を読みながら、鳥肌や笑顔を出してしまうくらい、登場人物の視点に立つことが上手でした。
このように、相手が話している情景をありありとイメージし、その時に感じた感情を自分も一緒に感じる。
これが共感の極意であると考えています。
とかなんとか言ってたら、共感と国語力は別物という記事を見つけてしまった。「共感」を理解するは難しい道のりだ。